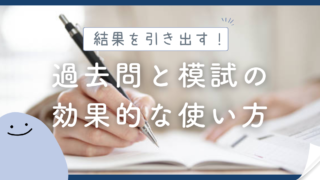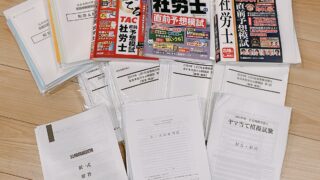記事内に商品プロモーションを含む場合があります
模試は試験対策において重要な役割を果たしますが、ただ解くだけでは効果が半減します。以下では、模試を最大限に活用する方法について解説します。
模試の目的を明確にする
模試を解く前に、その目的をはっきりさせることが重要です。以下のように目的に応じた使い方を意識しましょう。
- 時間配分の練習・実力の確認
試験本番を想定して、まずは決められた時間内に全問を解いてみます。時間配分の感覚をつかみ、現在の自分の実力を把握することが目的です。
- 苦手分野の克服
解いた後は、悩んだ箇所や知識が曖昧な選択肢を重点的に復習しましょう。問題に印をつけたりふせんを貼ったりしておくと、後から復習するときに探しやすくなります。覚えたらふせんを外すことで本を閉じた状態でも進捗が目に見えて分かります。
復習の徹底が鍵
模試は解いた後の復習が最も大切です。点数はあまり気にせず、以下のポイントを意識して学習を進めましょう。
- 間違えた問題を徹底的に分析
正解・不正解に関係なく、選択肢ごとにどこが間違っているのか、どの論点が重要なのかを考えます。曖昧な知識をそのままにしないよう、テキストで関連箇所を確認したりインターネットを活用して不明点を解決しましょう。
- 迷った問題も必ず確認
正解していても迷った問題は要注意です。特にマークシートの問題では、消去法でたまたま正解できてしまうことがあります。しかし、知識があやふやなままにしておくと、次に似たような問題に出会った時にも正解できるとは限りません。試験本番で「見たことあるのに解けない」と悔しい思いをしないために、しっかり復習しておきましょう。
- 本試験を意識した練習
答えを覚えるのではなく、選択肢を読み解く考え方を養うことが重要です。本試験では必ず初見の問題が出題されるため、この力を身につけておく必要があります。なぜその選択肢が正しいか、他の選択肢がなぜ間違っているかを自分で説明できない場合は、必ずテキストに戻って確認しましょう。
- 同じ予備校の教材を使う
自分が解いた模試の出版社が発行しているテキストを持っていれば、模試の解答解説にテキストの該当ページ数が記載されていることも多く、復習に役立ちます。こだわりがない場合は同じ出版社の教材を揃えると良いでしょう。ただし、複数の予備校の模試を受ける場合でも、それぞれのテキストを購入する必要はありません。使いやすいテキストを1冊用意すれば十分です。


模試スケジュールの立て方
模試を効果的に活用するためには、計画的なスケジュール作りが必要です。
- 複数回解く計画を立てる
模試は一度解いただけでは不十分です。1回目は本番同様に時間を測って全問解答し、2回目以降は苦手な部分に絞って繰り返し解くことで効率的に理解を深めることができます。
- 模試を解く日を固定
模試は復習まで終わらせようと思うと丸一日かかることもあります。休日は「模試の日」と決めて、平日はテキストを読んだりその他の問題集に取り組むことで無理のない学習が可能です。
- 学習計画にゆとりを持たせる
仕事や家庭の事情で計画通りに進まない場合もあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。あまり予定を詰め込みすぎると「予定通り進んでいない」と焦ってしまったり「このままではきっと試験日までに間に合わない」と受験自体を諦めたくなることがあります。「1日これくらいやる!」と決めても思うように進まないのが普通です。自分を過信せずにゆとりを持った学習計画を立てましょう。
模試から得た気づきを大切に
いくつかの模試を解いていくうちに「他の模試でも似たような問題が出ていたな」「法改正があった部分はこんな風に出題されるのか」などの気づきがあると思います。それらの気づきを大切に学習を進めましょう。
- よく見る問題は出題可能性が高い
複数の模試を解くことで、異なる視点からの出題傾向に触れることができ、本試験対策に有効です。模試は、各予備校が「本試験で出題される可能性がある」と予想した問題がたくさん詰まっています。複数の模試で似たような問題が出題されていたら、複数の予備校の講師が「本試験で出題される可能性が高い」と判断したということです。このような問題は特に重点的に学習しておく必要があります。
- 基本的な問題は必ずマスターする
模試では本試験を見据えた応用問題だけでなく、必ず押さえておくべき基本的な問題も出題されることが多いです。各予備校の公開模試などでは、マークシートを提出したりオンラインで解答を送信したりすることで、全受験生の正答率や個人の成績と順位を出してくれるものがあります。模試での順位や合格可能性の判定を気にしすぎる必要はありませんが、他の受験生の正答率が高い問題を間違えると点数に差がついてしまいます。正答率が高いのに間違えてしまった問題は、本番で必ず解けるように特にしっかり復習しましょう。
- 過去問にはない新問題の練習として
法改正や出題範囲の変更などがあった場合は、過去問だけを解いても対策できません。特に独学の場合は、どのような学習をするべきか分からず悩んでしまいます。一方で、模試はそれらの変更点も加味して作られているため、新しい問題の対策ができる貴重な教材となります。模試を解くことで、新しくどのような問題が出題されるのかイメージをつかむことができ、学習のみちしるべとなります。
まとめ
模試は「解く」だけではなく、「復習」こそがカギです。目的を明確にして解答し、迷った箇所や間違えた箇所を徹底的に分析することで、初めで見る問題にも対応できる応用力が身につきます。計画的なスケジュールで複数回解き、復習を繰り返すことで、模試の効果を最大化させて本試験での成功を手繰り寄せましょう。
ABOUT ME
スキルアップを目指して日々勉強する20代OLです。
社会人になってから独学で簿記2級、FP2級、TOEIC765点を取得。令和6年に国家資格である社会保険労務士試験に合格。
学習に関する情報などをマイペースに更新していきます。